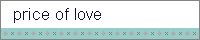人の気配に薄く眼を開いた。いつもと違う寝具の匂いがする――軍付属施設の病院か。
(ああ、また倒れたのか…)
今度は何日ぐらい眠っていたのだろう。
「あ、起きました?…先生」
「…ハボック君か」
涼しげな半袖、白と青。士官学校の制服は金の髪に良く映えて、カーテンの引かれた病室の中で、彼の周りだけがうっすらと明るく見えるようだった。
「すいません、ヒューズ准将じゃなくって」
「…また、名前を呼んでた?」
「はい」
我知らず呼んでいたのは他の男の名だというのに、馬鹿みたいにニコニコしている。雑種の大型犬めいて、どこかもっさりとした筋肉質で――だが、いかにも人なつこそうな碧眼の持ち主。
(私の学生…、私の年若い恋人)
乾いた唇を舌先で湿らせて、しかし声には出さずにそっと呟いた。
別に身体のどこが悪いというわけでもないのだ。むしろ、日頃は同年代の者に較べて壮健なくらいなのだが――彼、国軍士官学校教官ロイ・マスタングは、時折り何の前触れもなく意識を失くす。体温が著しく下がり、脈も間遠になる。その間は点滴で栄養を送り、導尿もしなければならないが、数日が過ぎるとけろりとして眼を開ける。
こんな身体になったのは、まだ今よりはだいぶ若かった頃。とある事件と前後してのことだったが――なんだか電燈のスイッチを点けたり消したりしているみたいだ、と彼はいつも思う。
「えーと、ロス中佐がこっそり教えてくださったんですが」
「うん」
「ヒューズ准将は1週間前から休暇をお取りあそばされて、お孫さんの顔をご覧になりにいらしたみたいっス…とかいうことでした」
「無理して敬語を使わなくても良いよ。今は二人っきりだし」
吹き出しそうになるのをこらえながら、片肘を支えにゆっくりと起き上がった。ハボックがすかさず、枕を背中にあてがう。
「それにしても、あいつが良くエリシア嬢を手放せたものだ…それもこんなに早く」
「なにしろ19才にして一児の母ですからねー」
そう言って妙に甲斐甲斐しく上掛けなど直しているハボックだって、似たり寄ったりの年まわりなのだけれど。こいつがヒューズ家の婿さんだったとしても、つり合い的には全然おかしくないのだ。
「しかし結局のところ、親バカがジジイバカに脱皮しただけだったな」
「子供ってそんなに可愛いもんですかね」
「さあ、よくわからないな…今のところ私は産む予定ないし」
「なんかいろいろ間違ってる気がしますが、突っ込みませんよ」
「子供時代の君なら、それこそ神の御使いみたいな可愛らしさだったろうとは思うが」
あははははもー何言ってんですかーと、あっさり受け流された。
(わりと本気で言ってるのに…!)
きっとおっさんが若いもんを適当にあしらってる、ぐらいにしか思われてないのだろう。ちょっと悲しい。
「…ハボック君」
「なんですか」
「起きる。少し歩きたい」
「そう言うだろうと思って、さっき呼出し釦を押しときましたよ」
「起きたかマスタング」
ハボックが言うそばから、昔馴染みの医者がスタスタと入って来た。
(見かけによらず気が利くんだよな…現役だったら副官に欲しかったな)
予備役に退いて、もう15年になる。最後の役職は東方司令部司令官、階級は大佐。さほど後悔はしていないが、こんな時には残念至極と思わないこともない。
体温と脈拍数と血圧を念入りに計測される。それからハボックはカーテンの外に追い出されて、導尿管をするりと引き抜かれた。一瞬のことで痛みも感じないが、何度経験してもいわく言いがたい気持ち悪さだ。挿入される時はいつも意識不明なのが、せめてもの幸いと言えるだろう。左腕の点滴を外されながら、そんなどうでも良いことを考えている。……
「便所はまだひとりで入るなよ。必ずそっちのヒヨッコと一緒に行け」などと念を押されてから、部屋を送り出された。ハボックは何を思ったか、ひとり赤面している。
上空から見ると、病棟は蜂の巣の一室を切り取ったような六角形をしている。外周にぐるりと病室が配されており、中心部にはやはり六角形の広い中庭を擁しているため、室内も回廊もきわめて明るい。「階段を使う」と言い張るロイをハボックはどうにかこうにかなだめすかし、妙に古風な昇降機を呼んで吹き抜けの中庭へと降りて行く。暖炉みたいな鉄格子を嵌め込んだ硝子戸越しに、地上の人影はぽつりぽつりとしか見えない。
ちん、と澄んだ音を立ててベルが到着を告げ、扉が開く。見上げる空はひたすらに高く、陽ざしもやや強いが、肌に触れる空気はからりと乾いていた。薄手の病衣の脇に片腕を差し入れて、軽く引き寄せる。
(あったかいや…良かった)
先生が臥せっていたあいだの、その両掌の感触がふと蘇りそうになる。半泣きでさすろうが息を吹きかけようが、彼の大好きな先生の手は氷漬けみたいにひんやりとしたままで、もともと血色の薄い肌が土気色に変わって行くようで――。
焔の錬金術師のくせして、こんなに冷たい。……
(…いやいや、大丈夫。もう大丈夫だから)
ハボックはぶんぶんと頭を振っておのれに言い聞かせ、分厚い手でロイの手を握りしめる。指もしっかりとからませた。
「君、暑苦しいぞ」
いかにも不機嫌そうな面持ちで、ロイはぼそっと呟く。それから、図体のやたらでかい教え子を見上げてにっこりと微笑み、さりげなく身体を預けてきた。
頑丈な杖のように寄り添いながら、ゆるやかに蛇行する小径を行けば、中庭のそこかしこに、ハボックが名前を知らない小輪の花がてんこ盛りに咲いている。眼もあやな梔子いろに躑躅いろ、あるいはやさしい杏いろが目を惹いた。
「――なんですか、この花は」
「衝羽根朝顔、かな。あるいはその近縁種か――この季節、よく見かけるね。士官学校の園芸部でも育ててたと思うよ。あとで誰かに聞いてごらん」
「そんな部活があったんだ…」
ひっそりと涼しげな樹蔭の一隅。ベンチの埃を軽く払って、ロイを先に座らせる。その傍らでもやっぱり、衝羽根朝顔は捨て鉢みたいな勢いで小花を咲かせていた。生育旺盛すぎて何だか雑草っぽいが、この場所には似つかわしい植栽のように思われた。
悪いけど、ぬるい水買って来てくれないか。それと新聞――と言われて、売店までひとっ走り。
陽のさかり、足下に伸びる自分の影が濃い。広々とした中庭を突っ切るのはそこそこ走りでがあるが、屋内の回廊をぐるりと巡るよりは遙かに早かった。売店の親父さんとは既に顔なじみである。マスタング先生が教壇でぶっ倒れるたびに、ハボックともうひとり、フランツ・ターナーという友だちが、病院にかつぎ込む担当みたいになってしまっているからだ。金髪の士官学校生が二人して病棟をうろうろしている姿は、なかなかに見舞客らの興味を引いたらしいが、これはまた別の話になる。
親父さんが奥の倉庫を開け、冷やしていない壜詰めの鉱泉水を出して来た。自分用の、きんと冷たいやつと一緒に栓を抜いてもらって、店を出る。彼方を眺めれば、樹下にぽつねんと座っているマスタング先生の姿。なんだかやけに遠く小さく見えたが、走れば水がこぼれてしまう――四つ折りにしたセントラルタイムズを小脇に、急ぎ足。
(あー、栓抜き借りてくりゃ良かったじゃん。おれバカじゃね?――つか、マジで先生の発作? 体質? ってどうにかなんねーのかな――あーっ、水ちょっとこぼれた…)
あらたまって聞いたことこそないけれど、ハボックにはおおよその見当がついている。寝物語のつれづれにロイが語ってくれたこと――心も身体もひとつにとろりと溶けたあと、夢のあいだで聞いた言葉の切れ端を綴り合わせて。15年前、何があったのか。先生がこんな身体になったわけ。
15年前――ヒューズ中佐は卑劣なる人造人間の襲撃を受けて、生死の境を彷徨った。有名な事件だから、これは誰でも知っている。命ばかりはとりとめたものの、来る日も来る日も意識が戻らぬままだった。
『――あの時の、あいつの両掌の冷たさを今でも覚えている。氷漬けみたいにひんやりとして。眼の前で土気色に変わって行くようで』
『病室を出ると、アームストロングが護衛の指揮を執っていて…、そこから先の記憶はどうもはっきりしない。あの気の優しい少佐の前で、泣いて何か訴えていた……ような気もする』
そしてまた、そのアームストロングさんちとは一族ぐるみのおつきあいという、ターナーの奴から聞いた話。
『あの家には、一子相伝のナントカ術というのが山ほどあるだろう。その中には、――を――するみたいな荒技が…とかいう話が昔から伝わっていて。錬金術とは全く別系統の。一説には超古代文明の遺産とも言われてるらしいが。僕は信じているわけじゃないがな』
口にこそ出さないが、もはや誰もが覚悟を決めていたという。けれど、ヒューズ中佐は息を吹き返した。その後しばらくしてマスタング大佐は予備役に退き、士官学校に赴任する。
物事を無駄に深く考えないのが取り柄のハボックだが、それでも一連のできごとは、磁石みたいに同じ向きを指しているように思われた。そしてヒューズ准将はといえば、あらゆる昇進人事から全力で逃げ回り続けていて、「なんか准将の階級にこだわりでもあるんですか」と部下たちを困らせているとも聞く。……
ぽたり、ぽたり。水のしずくはハボックの足もとへ続けざまにしたたり落ちた。ふと足を止め、来た道を振り向けば、名を教わったばかりの草花が風に花冠をそよがせる。乾いた黄色っぽい土の上には黒い地図ができていた。
帰り着く頃には壜の中身が微妙に目減りしていたが、ロイは受け取って美味そうに四半分ほど飲んだ。ごくごくと、白い咽喉が優美に上下するさまにうかうかと見惚れては、はっと我に返ったりなどしつつ、ハボックも自分の分をぐいぐいと飲む。
「――あ、そういえば。眼鏡…」
「持ってきてますよ」
「君、なんだかお母さんみたいだね。あまり甘やかすと私がバカになるよ」
「いっそ次年度は少しバカになる方向で行きましょう」
「何言ってるんだね、君は…」
ロイは呆れ顔で、ばさばさとセントラルタイムズを開いた。丸顔が老眼鏡かけて新聞を読んでいる。
「…まる三日寝ていたのか。それでも、だいぶ短くなった」
紙面に眼を落としたまま、独り言のように呟いた。例の小花は人の世のできごとなど素知らぬ顔で、わんわんと音立てんばかりに群れ咲いている。朝顔とは名ばかり、昼の陽ざしのもとでは原種の獰猛さを隠そうともしていない。その愛らしき草花が持つ、底抜けなまでの生命力――なんだかハボックみたいだ、と思うと少し可笑しくなる。そして当のハボックはといえば、視界の隅で何やらもそもそと挙動不審。……
「ちょっと…、ハボック君?」
顔を挙げもせずに訊いたものの、眼にははっきりと映っていた――いつとも知れずハボックがそっと手折った、ひともとの花は杏いろ。
「いちおう聞いておくけど。それ、私の頭に挿そうとか考えてないだろうな」
「おれの心を正しく読み取ってくださって、とても嬉しいです」
「おっさんの髪を可憐な花で飾っても、一般的にはあまり楽しくないと思うが」
「おれはそうでもありませんよ」
「そういう変わった趣味があること、あまり友だちには喋らない方が良いね」
「いえ、むしろ胸を張って…」
「やめたまえ」
ロイはとうとう我慢できずに笑い出してしまう。新聞を持ったロイの手首をハボックがひょいと持ち上げる。セントラルタイムズの蔭でキスをした。
「…ただの飾りじゃないんですよ」
「え?」
「お護りみたいなもんです。えーと、頭挿(かざし)の花?」
「頭挿? 君、どこでそんな話――」
ハボックの大きな手が頭の上を探るように動き、その一輪の花を髪に挿す気配。鏡も窓もない場所で、本当に良かった。
「いつだったか、座学の時間中に。たぶんエルリック教官の」
「ああ。超古代アメストリス文明特講」
「それです」
「ふうん…エドワードの奴も、たまには気の利いた話をするものだな」
山野の草木、人里の花のことごとくに宿る小さな神々に祈りを捧げ、その力を借りて厄災を遠ざけようとした往古の呪術。慕わしいのは、優しき心。遠く時を隔てて生きる人々の――そして今この時、傍らにある青年の。
「まあ、そういうことなら――、受け取っておかないこともない」
言いようの素っ気なさとはうらはらに、しずかに微笑んで眼を伏せれば、待っていたようにハボックの片手が伸びて来て、すっと眼鏡をはずした。そのまま、今度は深く唇をふさがれる――。
(私の学生…、私の年若い恋人)
――本当は、もうとっくに君から受け取っているのだけれど。返しきれないほど多くのものを。
ハボックの唇がわずかに離れ、今なんか言いませんでしたかと小声で問いかけた。
「何でもない…、何でもないよ」
「…先生」
「いつも肩書きで呼ぶね。私も君が任官されたら、少尉って呼ぼうかな。ハボック少尉。あんまり違和感ないね」
「そ、そうですか?」
ハボックは何だか柄にもなく照れている。制服の上からでも筋肉の形がわかるような身体が、ロイを壊れもののように抱きしめた。おかげで目隠しの新聞がばさりと落ちてしまったが、そもそも上階からは丸見えだ。何かまうものかとばかりに、短いくちづけを何度も交わすうち――ふとある変化に気づき、ロイは頬を緩める。
「……素晴らしいね、若いって」
ふふ、と覚えずこぼれ落ちた含み笑いは低く柔らかく、ハボックの耳をくすぐった。
「いっ…いやいや、それはそれで大変っていうか。良いことばっかでもないっスよ? 先生だって覚えがあるでしょう」
「うーん、どうだったかな。君と違って、私は昔からずっと淡泊なほうだし――」
「えっ? えええっ?」
「君、何か知らないけど驚きすぎだよ…」
さわさわと音を立て、緑蔭を渡りゆくのは南風。陽ざしはいまだ弱まる気配も見せないが、ただ風のみが夕暮れにさきがけて、頭挿の花をふわりと揺らして吹き過ぎる。
学パロがやりたかったはずなのに全然違う方向に爆走してしまいましたが、「夏だ!カレーだ!ハボロイだ!!」と叫びながら楽しく書きました。少しでも楽しんでいただけましたら嬉しいです。